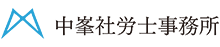- 確認
- キャンセル
-
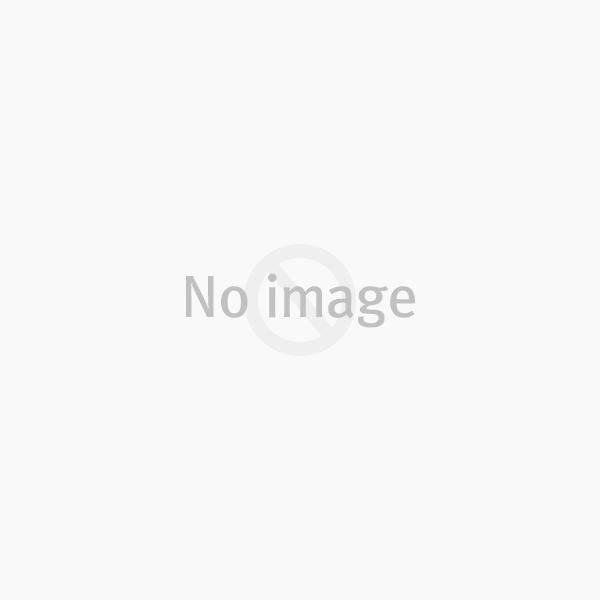
懲戒免職処分に伴う退職手当不支給の有効性
概要)退職金の支給については、裁判所が退職手当の支給制限処分の適否を審査するにあたって、軽重を論ずるのではなく、退職手当管理機関の裁量権の行使としてされたことを前提として、処分に係る判断が、社会観念上、著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、濫用だと認められる場合、違法であると判断すべき管理職ではなく、懲戒免職処分を除き、懲戒処分歴がない。30年間、誠実に勤務、反省の情を示していることなどを勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて、裁量権の範囲を逸脱し、濫用したものとはいえない。
2024. 01. 28
-
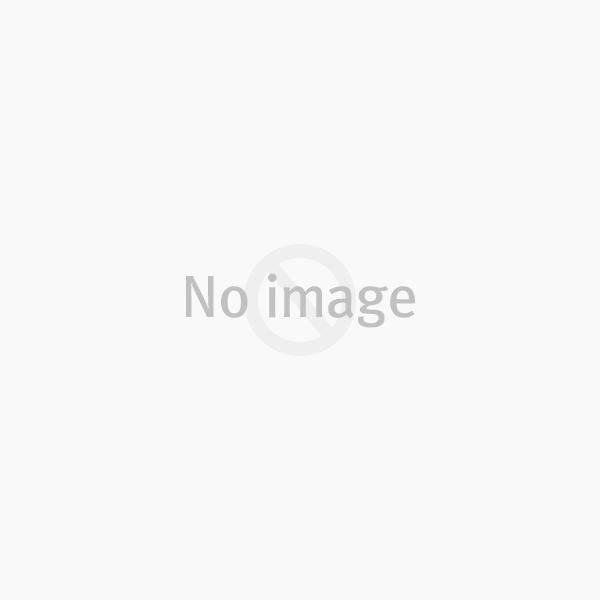
新給与体系に対して、賃金総額から基本給などを控除額を全て割増賃金とする給与体系の適法性
考察)給与体系を見直す場合に支払っていた手当をそのまま割増賃金に持っていくのは危ないと思われる。どれだけの時間外労働に対して、どれだけ割増賃金が支払われるかを明確にしていく必要があるかと思われる。概要)(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。道場などに定められた方法により算定された額を下回らない額の割増賃金を支払うことを義務付けるにとどまる。通常の労働時間の賃金に当たる部分と同条の割増賃金に当たる部分等を判別することができることが必要である。新給与体系は、その実質においては、労働時間や時間外労働の有無に関係なく、賃金総額を支払いば足りるように設定されている。給与体系の基本歩合給として支払われていた賃金の一部を名目のみを割増賃金に置き換えて支払うことを内容とする賃金体系にしている。本件割増賃金は、その一部に時間外労働等に対する対価として支払われているものを含むとしても、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含んでいるものと解さざるを得ない。本件割増賃金のうちどの部分が時間外労働などに対する対価にあたるかが明確になっているという事情も伺われない以上、割増賃金が支払われたものと言うことができない。
2024. 01. 09
-
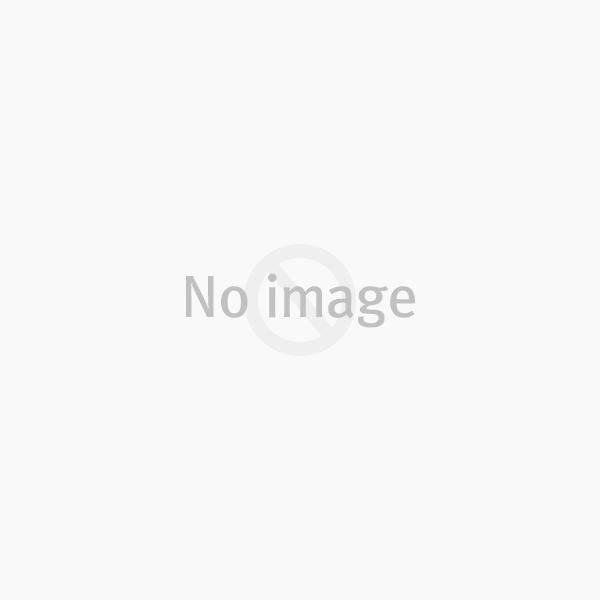
住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーの家事使用人該当性
考察)今回、家政婦と介護ヘルパーを兼業して行っていたが、介護ヘルパーの業務時間業務量については確認が取れ、こちらに疾病の要因がなければ家政婦の業務に問題があるとされたが、そもそも労基法の適用がないため、該当しないとされた。概要)家事業務は、KとAの息子との間の雇用契約に基づいて提供されており、これを本件会社の業務と認めることができない。(適用除外)第百十六条 第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。② この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。本件は家事使用人に該当するため、労災保険法上の業務起因性を検討する対象にならない。
2024. 01. 08
-
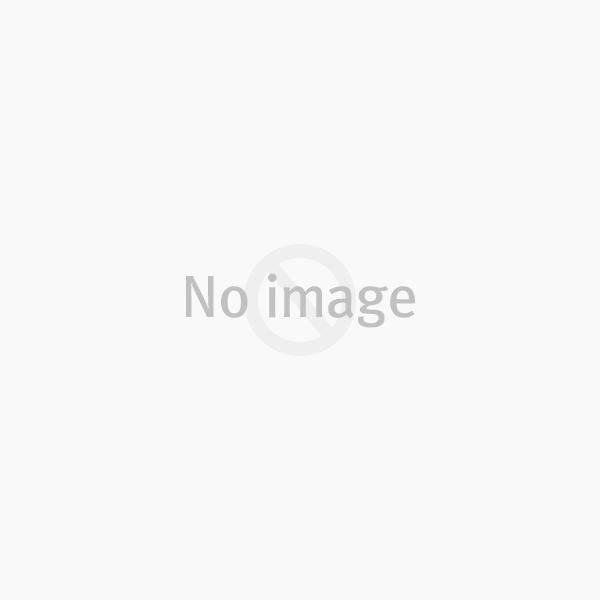
大学教員任期法に基づく期間雇用者の雇止めの有効性
考察)法律に応じて期間雇用が認められる事はあるが、詳細をわからずして使用することが難しく、5年以内の期間雇用を用いていることが妥当であると思われる。概要)大学教員任期法第四条 任命権者は、前条第一項の教員の任期に関する規則が定められている大学について、教育公務員特例法第十条第一項の規定に基づきその教員を任用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。一 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。二 助教の職に就けるとき。三 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。こちらの条文については、具体的事実によって根拠付けられていると、客観的に判断してることを要する本件講師職の募集経緯や職務内容に照らすと、社会における経験を生かした実践的な教育研究などを推進するため、大学以外から人材を確保する必要があるなどということができない。したがって、多様な人材の確保が特に求められる教育研究の職に該当するということはできない。ここの下線部分の箇所が、条文第一号に即しているかどうかが求められる。条文第3号に関しては、いわゆるプロジェクト研究、時限研究をいうと解され、数年先に学生募集を停止するといったような、もっぱら大学経営上の計画に基づき期間を定める教育研究は同号には含まれない。本件、労働契約10年特例の適用があるとは言えず、本件の時点において既に無期雇用契約に転換していたことになるから、労働契約上の地位を有するとされる。
2024. 01. 07
-
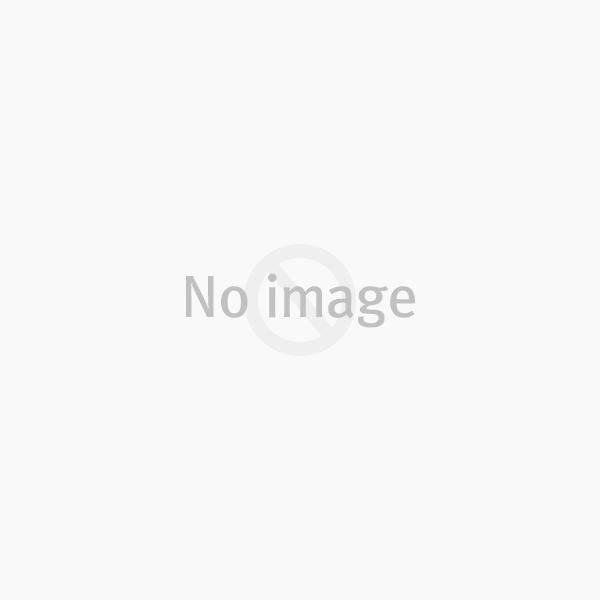
定年再雇用における65歳までの雇止めの適法性
考察)定年再雇用において、65歳までに更新満了による退職を求めるのは容易ではないことが分かる判例であると思われる。また、賃金の減額については就業規則などで記載をしている方が良いかと思われる。概要)労働契約法19条が適用対象とする有期雇用契約について、類型や条件などを限定する法令は特段存在していない。定年後の継続雇用であるからといって法の適用自体を否定すべき理由はない。(有期労働契約の更新等)第十九条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。人員整理を含む人経費削減の抽象的な必要性があったことは理解できる。Xに対して提示した賃金額は、当時の具体的状況においてやむを得ないものであるという根拠を具体的に検討したとは認められない。Xの勤務能力などを踏まえた相当な提示額である根拠もうかがわれない。Xは本件継続雇用制限上の上限である満65歳には達しておらず、本件雇用契約は、労働契約法19条2号により、再度更新されたとみなされた。本件雇用契約が本件継続雇用制度に基づく以上、合理的意思などを踏まえ、更新前と同一の労働条件の意味に本件継続雇用制度において定められた条件などに従うという趣旨を包含する例えば、継続雇用後の賃金の減額割合やいわゆる役職定年などの労働条件に従った更新という理解をすることもあり得る。本件継続雇用制度にそのような定めはなく、労働契約法19条2号を適用した効果として生ずる同一の労働条件での更新について、従前の雇用契約で定めるのと同一の労働条件によるほかない。
2021. 01. 29
-
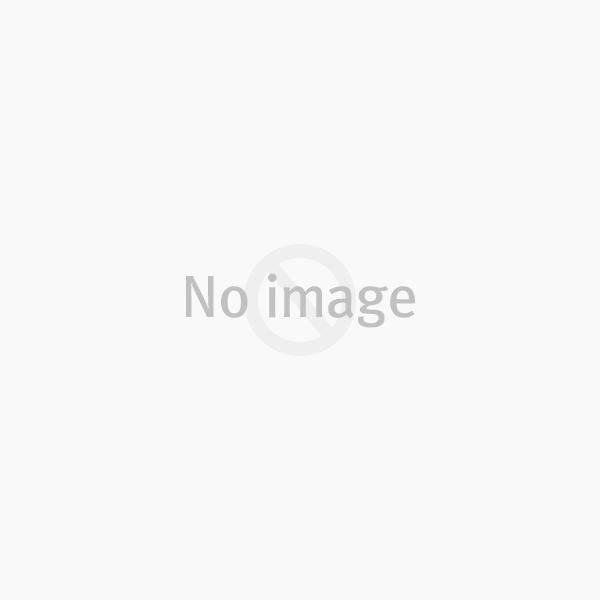
着替え中の労働時間性の有無
考察)着替えにおける労働時間の有無については、よく話になるが、その内容についての一つの参考になるかと思われる。賠償については、基本的に規定を守って行われている場合については、認められるケースもありそうである。概要)制服を着用することが義務付けられ、朝礼の前に着替えを済ませることになっている。その時間及び朝礼の時間以降は、指揮命令下に置かれたものと評価することができる。これに要する時間は、それが社会通念上相当と認められる限り、労働基準法上の労働時間に該当するというべきXらが引越し事故責任賠償金名目で支払った金員について、賠償規定が定める手続きを全く履践していない。金額についても、同規定が予定しているものとは全く別である。同規定に基づく引っ越し事故責任賠償金であるとは到底認められない。賃金からの控除または現金交付の方法により賠償金名目で支払ったことには法律上の原因がない。通勤手当は、労働契約に期間の定めがあるか否かによって通勤に要する費用が異なるものではない。職務の内容及び配置の変更の範囲が異なることは、通勤に要する費用の多寡とは直接関係するものではない。労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当
2021. 01. 20
-
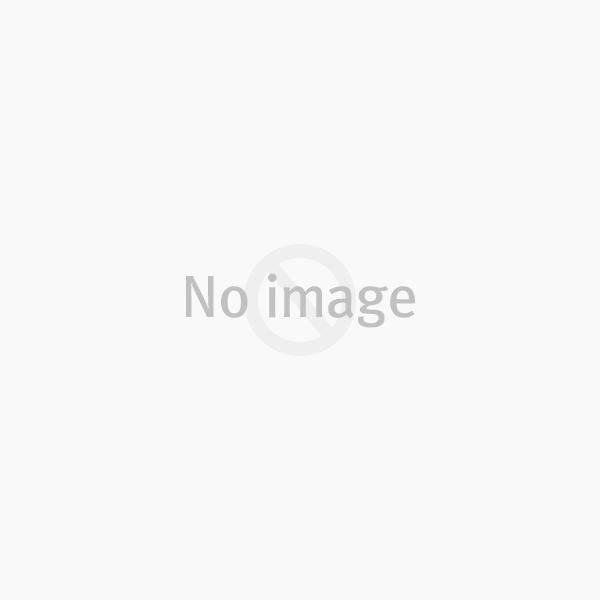
整理解雇における解雇対象者の優先順位について
考察)基本的な整理解雇の4要件を話されている判例であると思われる。職種限定合意の従業員においても、配転の必要性がなくなる訳ではなく、定年再雇用者は優先して整理解雇の対象とできる可能性はありそう。概要)職種限定合意があっても、直ちに整理解雇法理の適用が排除されるわけではない学部廃止に伴う教員の過員状態の改称という人員削減の必要性自体は認められる。Xらを解雇しなければY法人が経営破綻するなどの逼迫した財政状態ではなかったXらを解雇する必要性が高かったとはいえない。異動させることを検討しておらず、総人件費削減に向けて努力をした形跡もない。解雇回避努力が尽くされたとはいえない。人選の合理性を肯定することは困難である。Yは多数回の団交に応じるものの、希望退職の募集と解雇対象者の事務職などへの配転を検討するのみ協議が十分に尽くされたと言い得るかは疑問が残る。整理解雇法理の4要素を総合考慮しても、労働契約法16条所定の客観的合理的理由と社会通念状の相当性は肯定されない。人員削減の必要性が認められる場面において、定年後に再雇用されて有期労働契約を締結している労働者を雇止め退職金を受けた後、1年の有期労働契約を締結したものであり、無期契約者と比べ、経済的打撃や雇用継続への期待は大きいとは言い難いXら2名の雇い止めについて、人員削減の際に有期契約労働者を優先して雇い止めとすることには客観的に合理的な理由があり、社会通念上も相当
2021. 01. 20
-
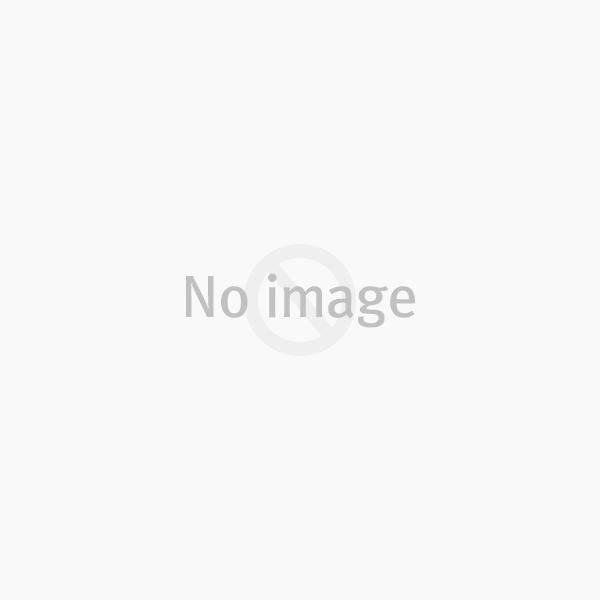
有給休暇の取得方法の有効性
考察)有給休暇の取得について、今回の判例のようなケースであっても良いと考えれるのは、これからの有給休暇の取得義務を考える上で、選択の範囲が広がる有意義なものであると考えられる。概要)B賃従業員とY社との間では、それが合法か否かは別として、ここの欠勤ごとに有給休暇取得の有無を判断するのではなく、結果的に、所定労働日数8乗務16日を下回らない限り、有給休暇を取得しないものとして扱われていたものと推認仮に、有給休暇がないといった趣旨の発言があったとしても、それは、現実にはB賃従業員の中で月の乗務数が8乗務を下回るものがいなかったことを踏まえて、当事者間の認識を確認ないし説明する趣旨のものであったと理解することができる。
2020. 10. 02
-
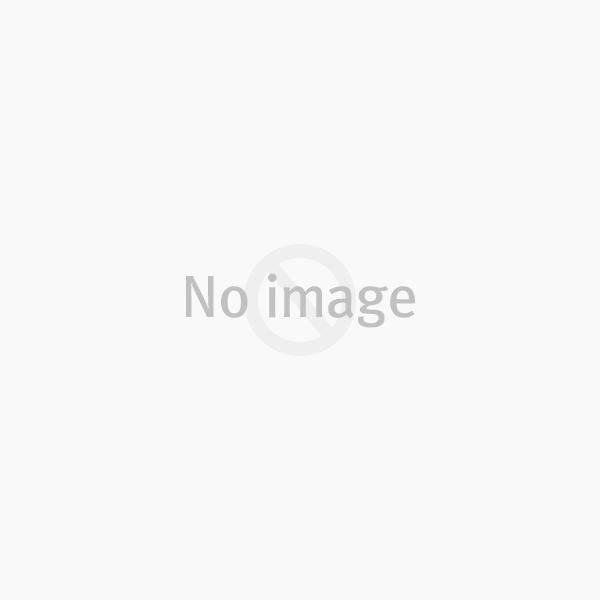
新しい職場で働いている元従業員の地位確認の有効性
考察)新しい職場で働いていたとしても、いつでも復帰のできる契約形態の場合、地位確認が認められる可能性があるという判例であると思われる。地位確認が認められる場合に、中間利益が全ての賃金の控除にかかる訳ではなく、6割の休業手当は必ず支払う必要があることは参考になる。概要)Xらの賃金請求について、解雇された後、それぞれ新たに就労などすることで収入を得ている。しかし、Y社における賃金額に及ばず、新たな就労などの形態も、Yとの労働契約上の地位が確認された場合には復帰することが可能なものと認められる。Xらは、解雇の意思表示があった後の期間中の賃金請求権を失うことはない。しかし、将来の給付請求をするまでの必要性は肯定できず、却下を免れない。解雇期間中にXらが得た収入は、中間利益としてXらの平均賃金の6割を超える部分から控除される。(会社都合のため、6割は支給義務がある。)将来の給付請求:まだ到来していない債権や条件が成就していない将来の権利を主張する場合は、あらかじめ勝訴判決を得ておく特別の必要性が認められれば許されるが、そうでない限り利益のない訴えとみなされる。(あらかじめその請求をする必要がある場合として認められるか否かは、被告の態度や給付義務の目的、性質などを考慮して判断される。)
2020. 10. 02
-
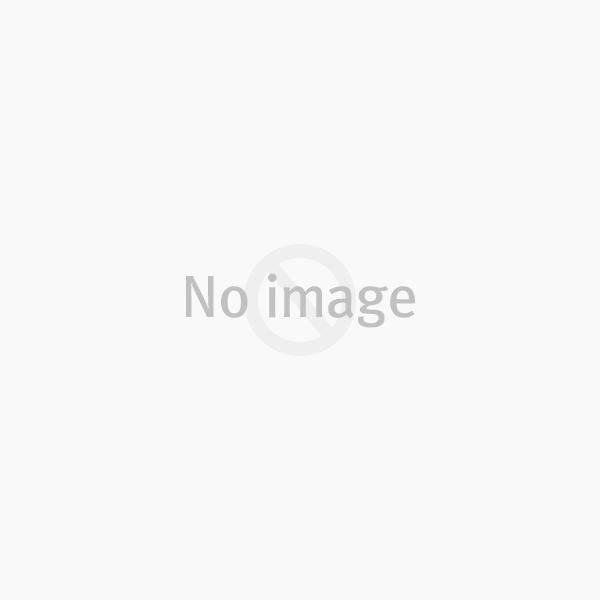
裁量性のある業務の長時間労働における安全配慮義務違反の有無
考察)安全配慮義務についての判例である。長時間残業だけをもって安全配慮義務違反を否定したことについては、参考になるが、今回のような裁量性のある業務についてのみの限定的な判例であると思われる。概要)使用者は、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷などが過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことが内容注意する労働契約上の付随義務(安全配慮義務)Xの業務がうつ病の発症をもたらしうる危険性を有する特に過重なものと認識することは困難長時間労働のみをもって、うつ病の発症を予見できたとは言えない。Xの業務をさらに削減することが困難であった上、Xから業務の遂行が困難であることの申告もなかった。回避するための具体的な対応をすることも困難であった。①調査研究部における業務は、個別性が強く、研究員には自らの担当業務について、裁量性がある。②自らの業務の進め方について上司や同僚に相談しなかった③Xの業務の内容は、他の主任研究員と比較して、その質又は量が特に過大であるということもなかった
2020. 09. 29
-
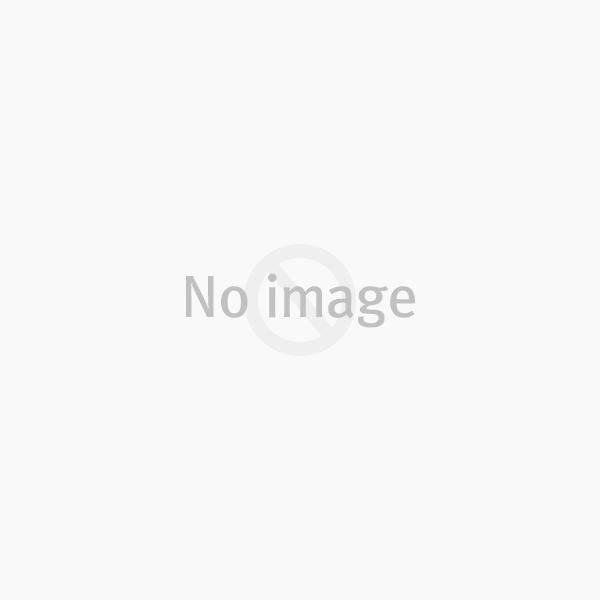
労働契約法20条におけるその他の事情の有効性
考察)労働契約法20条における不合理性を争ったものであるが、その他の事情が大きく影響した判例であるといえる。概要)出産手当金として、無期契約社員は出産休暇を付与され、通常の給与を支給される一方、有期契約社員は健康保険上の出産手当金の支給しなされない。労働条件の相違は、労働契約法20条にいう期間の定めがあることによる労働条件の相違に当たる。しかし、Y法人の女性職員の比率に照らすと、当該制度の目的にはY法人の組織運営の担い手となる職員の離職を防止して人材を確保するとの趣旨が含まれており、その趣旨が合理性を欠くとは認められない。労働条件の実質的な相違が基本的には通常の給与額と健康保険法上の出産手当金との差額部分に留まる事も考慮すると、無期契約職員及び有期契約職員の処遇として均衡を欠くものとはいえないとして均衡を書くものとはいえない、労働契約法20条にいう不合理性を否定全職員に対して付与・支給を行うことも合理的な一方策であるが、Y法人の相応の経済的負担を伴うものであって、これをいかなる範囲において行うかはY法人の経営判断にも関わる事項である。
2020. 08. 31
-
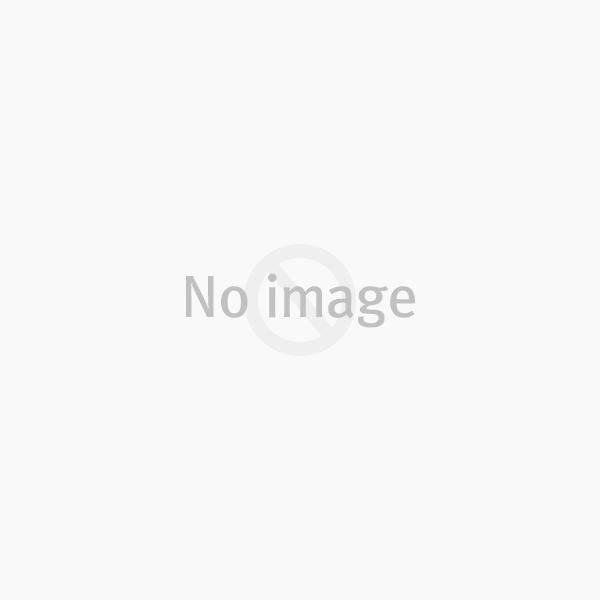
業務の異なる配転命令の有効性について
考察)配転命令における参考となる判例であると思われる。やはりネックとしては、不利益の大きさと、これまでに同じような配転命令が行われていたのか?というところでしょうか。概要)転勤命令について業務上の必要性が存しない場合または業務上の必要性が存する場合であっても、転勤命令が他の不当な動機・目的をもってなされたものである時、もしくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなど、特段の事情が存する場合には、配転命令は権利の濫用として無効業務上の必要性:複数の業務を経験させることによって人材の育成を図るため。X以前にも、事務職員が営繕室において勤務をしていたこともある。不利益:学校の構内における勤務場所の変更に過ぎない。執務環境も、他の事務職員の勤務する場所に比して劣悪であるということはできない。業務の内容も、事案決定書の作成などの事務作業であり、精神的または肉体的な負担が大きいものではない。得意とする広報業務に携われてないとしても、担当する業務を限定する旨の合意が成立していたことを認められない。著しい不利益を負わせるものということはできない。
2020. 08. 31
-
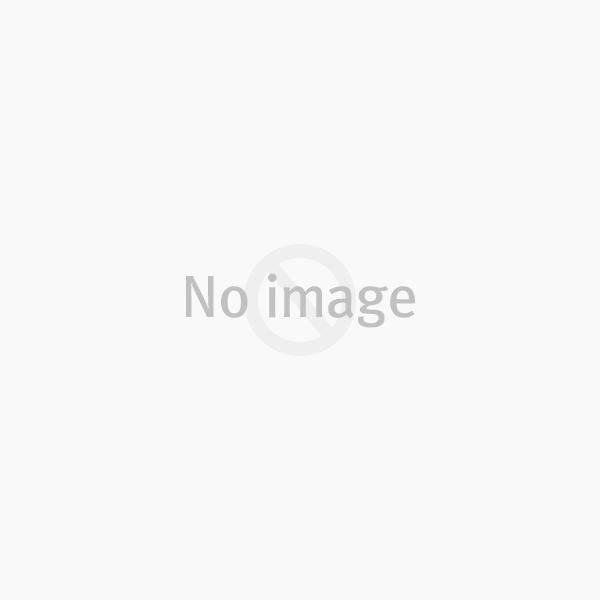
長時間労働とうつ病発症との因果関係について
考察)重要なところとして、業務内容が通常どの程度の労働時間を要するかという面に着目した。逆に、労働時間が長時間に渡ったとしても、その時間が通常どの程度かによって少しは判決の内容が変わるのか?概要)各種業務のために長時間労働を継続Xの業務は著しく過重なものであった。本件発症前6ヶ月におけるXの時間外労働時間は129から164時間であったと認定「厚生労働省が策定した労働災害の業務起因性に関する認定基準」において、心理的負荷の強度が「強」となる出来事として発症直前の連続した2ヶ月間に、1月あたり概ね120時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった。相当因果関係が認められる。Y社がこれを解消すべく、業務量の軽減するための措置を講じたものとは認められない。安全配慮義務違反があったものと認められる。
2020. 08. 31
-
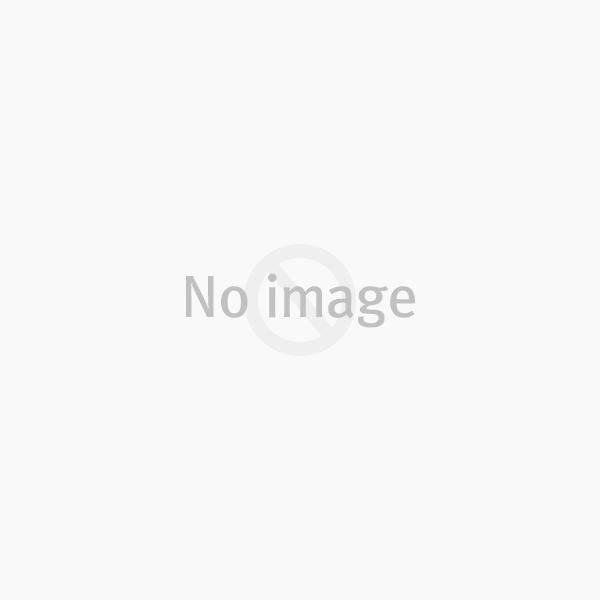
長期間の契約を続けている臨時職員と正規職員の労働契約法20条違反の有無
考察)長期間の契約を続けている臨時職員において、労働契約法20条違反を認められるケースが大きくなると考えられる。概要)正規職員と臨時職員の間では、業務の内容および当該業務に伴う責任の程度に違いがあるということさらに、可能性だけでなく、実際上も職員の内容および配置の各変更の範囲において相違があるということができる。1ヶ月ないし1年の短期という条件で、人員不足を補う目的のために4年間に限り臨時職員として採用30年以上もの長期にわたり雇い止めもなく雇用させる業務に対する習熟度を上げたXに対し、臨時職員であるとして賃金の引き上げのみが行われた。同じ頃採用された正規職員との基本給の額に約2倍の格差が生じている。同学歴の正規職員の主任昇格前の賃金水準を下回る3万円の限度において不合理である。労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当である。労働契約法20条違反の取り扱いをしたことには過失があったというべきである。
2020. 08. 15
-
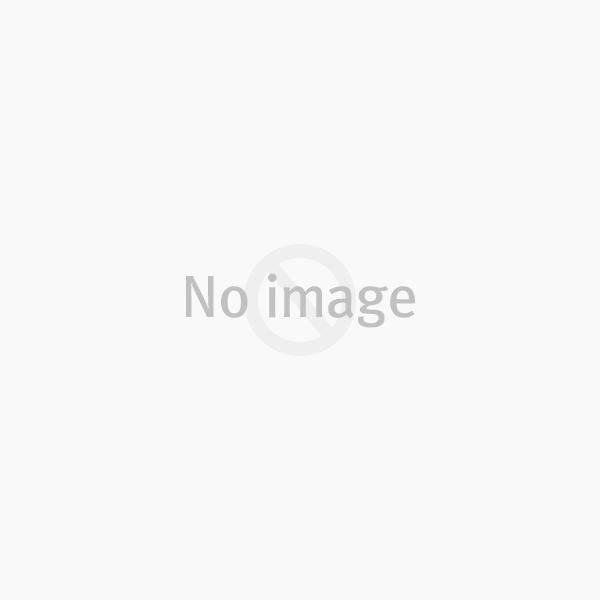
正社員と契約社員の賃金項目ごとの不法行為の有無
考察)正社員と契約社員との相違について、賃金項目の趣旨を個別に考慮した上で、それぞれの説明がなされていることが分かりやすくて良い。休暇についても反映されており、参考になる。概要)労働契約法20条には、補充的効力はなく、「不合理なものと認められる」として無効とされた場合、労働条件に基づく取り扱いには不法行為は成立し得る。しかし、就業規則および給与規定などの合理的解釈として、正社員の労働条件が有期契約労働者に適用されるということはできない。不合理性の判断は、賃金総額を比較することのみによるのではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべきである正社員と契約社員両者の間には、職務の内容ならびに職務の内容および配置の変更の範囲に大きな、または一定の相違がある上、正社員には長期雇用を前提とした賃金制度契約社員にはこれと異なる賃金体系を設けることは一定の合理性が認められる。外務業務手当職種統合による賃金額の激変を緩和するため基本給の一部を手当化したもの契約社員については、賃金体系において、外務加算額という形で別途反映されている。不合理なものとはいえない。年末年始勤務手当契約社員が年末年始の期間に必要な労働力を補充・確保するための臨時的な労働力であるとは認められない。支払わないことは不合理であると評価することができる。住居手当正社員は転居を伴う配置転換などは予定されていない。労働契約法20条にいう不合理なものと認められる。差額全額につき不法行為に基づく損害賠償が認められる。夏期冬期休暇および病気休暇につき、正社員と契約社員らとの労働条件の相違は労働契約法20条にいう不合理なものと認められる。ただし、夏期冬期休暇が付与されなかったことにより賃金相当額の損害を被った事実の主張立証がないことから、損害が発生したとは認められない。正社員に対し私傷病の場合は有給とし、契約社員に対し私傷病の場合も無給としている相違は不合理であると評価することができる。病気による無給の承認欠勤および年次有給休暇取得日について、病気休暇を取得した場合に支給される額の不法行為に基づく損害賠償請求が認容される。慰謝料請求については棄却
2020. 08. 14